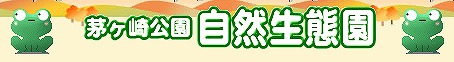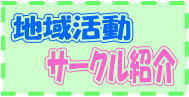 親子で体験 昔ながらの手作業 親子で体験 昔ながらの手作業 |
||
 稲の脱穀作業のレポート 稲の脱穀作業のレポート |
||
 |
||
| 平成25年11月9日(土)10時から2時頃まで茅ヶ崎公園の自然生態園の 「稲の脱穀作業」がおこなわれました。 サポーターと呼ばれる年会員の親子さんたちが大勢集まり、6月の田植え から、6ヶ月間かけて育てられたその稲は、稲掛けにかけて乾燥されてお りました。脱穀のために親子総出で下す作業から始まった脱穀体験は親子 の共同作業そのもので、見ていてとても微笑ましく思いました.。 |
||
 |
||
| |
||
 |
茅ヶ崎公園自然生態園管理運営委員会の 亀田さやか(理事/事務局長)さんは、 開園前からイベントの準備のため忙しく動かれており、タイミングを見計らって、次のようなご質問を投げかけ、お答えをしていただきました。 |
|
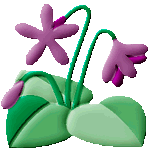 |
 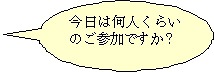 |
|
| |
||
(解説) 明治時代末になると、足踏式脱穀機が 開発され普及するようになった。 足踏式脱穀機は、人が踏板を踏むと こぎ胴が自動的に連続回転するよう に工夫されています。 |
 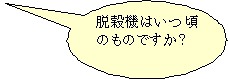 |
|

|
前です。 |
|
 |
||
| |
||
















 皆さんお疲れ様でした!
皆さんお疲れ様でした!