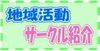 |
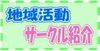 |
 |
 |
横浜歴博もりあげ隊という名前は、横浜歴史博物館(以下歴博)の博物館感謝デーなどイベントがある時に、よく目にする。会員は、歴博の職員ではなさそうだが、とても生き生きしているうえに、来場者にもにこやかに接している。
ということで、代表の佐伯さん(右)、副代表の杉木さん(中)、副代表の片山さん(左)に集まっていただいた。 密なスケジュールの合間だったが、終始なごやかな雰囲気の中で話は進んだ。みなさんの「歴博に足を運んでもらいたい。イベントを盛り上げたい。歴史好きを増やしたい。自分たちも楽しみたい」の気持ちが伝わってくるひとときだった。
「もりあげ隊というネーミングがいいですね。盛り上げたい!の意味が込められているのですね。隊の設立はいつでしょうか」 「歴博を市民目線で応援する会として、2013年の5月に立ち上げました。去年、5周年記念の行事をしたところです。歴博とは情報交換もしますし助言は受けますが、あくまで独立したグループです」 「横浜縄文土器づくりの会は20年ぐらい前からあります。それと、横浜古文書を読む会、横浜古代史料を読む会、大塚・歳勝土遺跡をガイドする横浜さいかちの会の4団体で、歴博と連絡を密にとりあって歴博を支援しようと、2008年に関連団体連絡会を発足させました。さらにより実践的な歴博支援を目標に、そこから独立したのが横浜歴博もりあげ隊です」 「これらの5団体は関連団体連絡会を作って協力しているだけでなく、たとえば古文書を読む会に属しながら、もりあげ隊の会員にもなっている方がたくさんいます」 「もりあげ隊の会員は何名ですか」 「現在は男性が31、女性が16の47名。多少の入れ替わりはありますが、ほぼこの人数です。年代は50代から80代まで、いちばん多いのは70代。会員の高齢化が気になります」 地域活動の取材をしているとたびたび感じることだが、ほとんどの会で若年層の参加が少ない。とはいえ、高齢者にはいろいろな場を経験してきたからこその知恵がある。戦争を覚えている世代もいる。もりあげ隊の会員も、専門の学芸員が思いつかない素人ならではのアイディアを提供できるかもしれない。もりあげ隊のアイディアが歴博の展示などに活かされたら、どんなに楽しいことか。 「ここ1年間(2018年8月から2019年7月)の具体的な活動を教えてください」 「大きなイベントは年に2回の一般公開の講演会です。去年の12月には『転換期の皇位継承 キサキからみた幼帝の登場』を国士館大学准教授の仁藤智子氏にお願いしました。今年の6月には『見えてきた青海路ーもうひとつのシルクロードー』を、奈良芸術短期大学教授の前園実知雄氏が、話してくださいました。講演会は大人気で抽選になることが多いんです」 「演題や講師は、もりあげ隊が決めているんでしょうか」 「そうです。もりあげ隊で決めてから、歴博にご相談することが多いですね。歴博のご紹介があると、話はスムーズに進みます。歴博主催の講演会は、主に 「6月22日には、やはり一般向けに『初夏のバロック・コンサートin歴博』も開催しました。湘南バロック・アンサンブルの方の演奏でした。エントランスホールという場で聴く演奏会も大人気です」 取材の交渉をしたのが6月初め。ラッキーなことに続いて大きな催しがあり、取材がてら参加することができた。これほどの大きな行事をスムーズにこなす「もりあげ隊」の実力に感心してしまった。
「会員と関係団体向けですが、会員の友人・知人も参加できます。歴博サロンも年に2回です。去年の10月のサロンは、横浜都市発展記念館の青木祐介副館長の『横浜生まれのフランス瓦』の話でした。今年7月のサロンは歴博の石崎康子主任学芸員による『横浜市の市史編纂事業と横浜開港資料館』です」 写真は研修室で行われた7月の歴博サロン。石崎学芸員(左に立っている方)は、開港資料館勤務時代に企画した展示会の裏話や、横浜市史の編纂事業が3回行われた経緯を詳しく話してくださった。学芸員の視点ならではの、興味深い内容だった。
博物館や歴史に興味をもってもらうためのワークショップは、1月末から2月初の博物館感謝デー、3月のつづき人交流フェスタ、6月の開港記念日、8月の夏休みに行われる。また5月の大塚遺跡まつり、10月の遺跡アート展に参加したこともある。 「どんなワークショップをしているのですか」 「今年の2月2日と3日の博物館感謝デーには、あじろ編みの小物入れ作りを指導しました。そのためには私たちも練習します。まちがい探しというクイズラリーと参加賞として缶バッジ作りもしました。大勢の子どもたちが参加してくれて張り合いがあります」 「夏休みにもあじろ編みのワークショップを行いました。中国結びでストラップやミサンガを作ることもあります。開港記念日には缶バッチ作成を指導しました」
「今年の4月にはお花見バスツアーとして山梨県の美術館や博物館を訪問してきました。ボランティアの解説を聞き、同じボランティア同士で交流もできました」 左は山梨県の釈迦堂遺跡博物館を見学している写真 「他に支援していることはありますか」 「エントランスに置いてある提案箱を定期的に開けて、意見や感想を集計し博物館に報告しています。報告書は博物館活動の参考になっているようです」 「”学校に歴史資料室をつくっちゃおう”という歴博の事業のお手伝いもしました。現在は、文化庁支援事業の”よこはま地域文化遺産デビュー”の実行委員会のメンバーになっています」 歴博を支援し盛り上げる活動は、このように広範囲に渡っている。
「もりあげ隊に関わるようになった動機を教えてください。まず佐伯さんから」 「学生時代は、日本史は嫌いだったんです(笑)。でも職場で調べなければならないことがあり、それがきっかけで楽しく勉強しようという気になりました。夫のタイ赴任に同行した時に、バンコクの国立博物館で日本人向けのガイドをしました。帰国後、神奈川県立博物館で5年間のガイド。こんな経験が今に生きていると思います」 「杉木さんはどうですか」 「関西育ちということもあり、若い頃から古代史に興味がありました。勤めている時も通信大学で勉強していましたが、時間が足りません。そんなとき、阪神大震災があり、生きているうちに好きなことをやろうと会社を退職。最初に接点を持ったのが、歴博が募集した縄文土器作り教室です。5倍もの倍率だったそうです。古代史料を読む会にも参加するようになりました」 「片山さんは何が動機でしたか」 「仕事は理系でしたが、もともと古代史が好きだったのです。定年後に歴博の古代史講座を受けたのがきっかけで、古代史料を読む会に参加しました。今は古文書を読む会にも属しています。好きな勉強も出来るし、ボランティアもできる。ボランティアは、会社勤務とはちがう楽しさがあります。子どもが喜ぶ顔をみていると心がいやされます」
3人ともお住まいは都筑区ではない。佐伯さんはかなり遠い栄区、杉木さんと片山さんは近いとはいえ港北区である。でも楽しそうに活動している姿に接すると、嬉しくなってくる。歴博のためにも、市民のためにも、自分の楽しみのためにも、「もりあげ隊」をこれからも盛り上げて欲しいと切に思った。誠実に対応してくださったみなさんに感謝したい。 もりあげ隊は会員を募集している。入会のお問い合わせは moriagetai.yr@gmail.com まで。 (2019年6月・7月訪問 HARUKO記) |
||||||||||||||||||||||||||