 |
| 茅ヶ崎公園 生態園 ”稲刈り” |
|
 |
|
10月4日(土)「稲刈り」も晴天に恵まれ、10時の集合時間前には、すでに60名ほどの親子会員の方集まっておりました。
「米づくり」のイベントも、
→4月27日(苗床づくり)
→5月24日(田起こし、しろかき)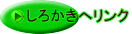
→5月31日(田植)
→7月5日(田の草取り)
→8月23日(稲の観察)
→9月6日(かかしづくり)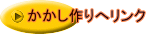
米作りも後半にさしかかっております。
スタッフの方の「稲刈り」についての予定と注意事項があり、その後思い思いの服装で、稲刈り用の鎌を持って田んぼに入って行きました。
|
|
 |
 |
 |
| 横一列に並んで、柔らかな土に足を取られながらも、意外とスムースに刈り取られて行きました。 |
 |
 |
 |
| 子供たちの稲刈りですが危険な「鎌」を使いこなせるか見ていましたが、意外や怪我もなく刈り取っておりました。 |
 |
 |
 |
| 刈り取られた稲をボックスにいれる子供たち、稲を束ねる人、役割分担と連携プレーがとても行き届いておりました。 |
|
|
 |
|
親子の皆さんが稲の束をに取り組んでいる間、スタッフの方たちは、竹などを使って「稲掛(はざかけ)」を田に組む作業に取りかかっておりました。 |
 |
|
はざかけ(稲掛、稲架).
稲刈り直後の籾(玄米)はそのままでは水分量が多過ぎるので、乾燥させる必要があります。水分が多過ぎると、保存中に味、風味が悪くなり、ひどいときにはカビが生えたりします。そこで、陽あたりがよく風通しのよいところに干し、時間をかけてゆっくりと自然乾燥させます。
この自然乾燥は,竹などを使って組んだもので、その上に刈り取った稲を掛け,そして天日でじっくり乾燥させます。
まだ刈り取り機や乾燥機の無い頃には、みんなが行っていた乾燥方法ですが、手間暇がかかるため沢山の人手を必要とする大変な重労働でした。
乾燥機の普及に連れて「はざかけ」の風景は次第に消えていきましたが、今また、天日干しの大切さが見直されはじめ、「はざかけ」をする農家が増えてきています。 |
|
|
 |
|
ここ生態園では、親子会員の方とスタッフの皆さんの協力で、刈り取った稲を逆さにして、天日乾燥の「稲掛(はざかけ)」を行っています。 |
 |
|
何日もかけてゆっくりと乾燥させることで、茎に残った旨味を米一粒一粒に行き届かせ、お米一粒一粒が完熟した状態になって、さらに美味しいお米に仕上げてくれます。
「はざかけ」をすると、その期間で熟成が進み全体的に完熟、または成熟したお米になるといわれます。これが「はざかけ米」が美味しいといわれる理由の一つです。
この刈り取られた稲は、11月8日「脱穀」まで、「かかし」に守られながら、天日干しされます。 |
|
 |
|
稲刈りの時、稲穂の先に「カマキリの卵がありました。
来年には沢山の赤ちゃんが生まれてきます!。 |
 |
|
<カマキリ事件>
レポーターの私ごとですが、稲に隠れていた「カマキリ」や「イナゴ」たちは、稲が刈り取られるにしたがい、追われるように畑の外に逃げ惑っておりました。
その一匹(カマキリ)が左の写真のように、クモの巣にひっかかり逃げようともがいているのを見つけ、助けようと体を乗り出し、柵に体重をかけた瞬間柵が折れ、カメラを持ったまま顔から畑の脇に流れる川に落ち込み泥まみれになりました。
取材用のカメラは向かいの土手に転がっており、汚れてはいたが泥沼の中ではなく助かりました。体は泥沼の中で起き上がるのも大変でした。みっともない姿を見せまいと稲刈りで汚れた子供たちに紛れ込みました。
え〜っ!肝心の「カマキリ」はどうなったか?ですって!
クモの巣が私の頭に付いていましたので、助かったとおもいますよ、お礼の言葉はなかったですけど・・・・。
こんなに文面スペースをとってしまいすみません。 |
|
|
今後の予定は、11月8日(脱穀)→23日(もみすり、精米)→12月6日(もちつき)となっております。
ご覧になりたい方は、生態園に是非お越しください。お待ちしています。 |
11月
「脱穀」干した稲穂を足踏み脱穀機で,もみ米をはずします。
「精米」を行います。
30kgくらいのもち米が出来上がります。収穫の喜びを感じるひとときです。 |
12月
「お餅つき」
蒸しあがったもち米を「臼」「と「杵」で餅つきをします。会員皆さんで醤油もち、きな粉もち、あんこもちにして食べます。味は最高です |
|
|
|
| 親子が集う「コメづくり」の一環の”稲刈り”ですが、子供たちは自然と触れ合いながら、楽しそうにお父さんや、お母さんのアドバイスを受けながら「稲刈り」や「はざかけ」に取り組んでおりました。 |
 |
つづき交流ステーション
レポーター 濱ちゃん
取材2014.10.4 |
|
地域活動サークル紹介に戻る
つづき交流ステーションに戻る |
|

